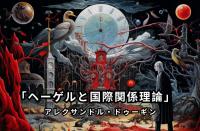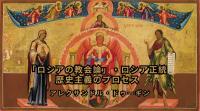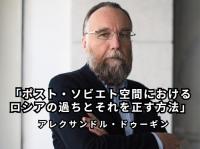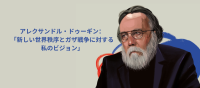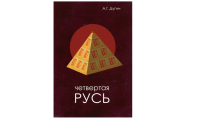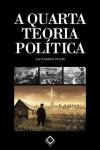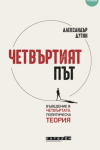テキサスでの出来事・新たな内戦か?
プラグマティズムの発祥地であるアメリカで、その思想は失われつつあると言えます。特にバイデン政権下のグローバリストたちは、チャールズ・パイスやウィリアム・ジェイムズによって確立されたアメリカの伝統的な価値観との関係を断ち切り、グローバリズムの極端な形態を表現しています。プラグマティズムの伝統は、主体と客体に対する規範的内容の処方に対して完全な無関心に基づいており、真のプラグマティストにとっては、主体が自己、対象、あるいは他の主体に対して持つ認識は無関係であり、重要なのは相互作用において全てが効果的に機能することです。しかし、グローバリストたちはイギリスの実証主義者やフランスの熱烈な唯物論者に近い考えを持ち、全体主義的な態度で、自らの規範に従うべき対象を指示しています。
「聖書プロジェクト」の終焉
資本主義の社会的性質とそのグローバルな規模により、このシステムの危機は連鎖反応を引き起こすトリガーとなります。この危機は資本主義だけでなく、一般的な社会システムをも超える危機メカニズムを動かすのです。現代社会と進歩的な思想、マルクス主義と自由主義、それに関連する科学や教育の組織形態、啓蒙の時代の地球文化全体の危機についてはすでに多くが論じられていますが、特に19世紀の「長い50年間」つまり1848年から1867年の間(1848年のヨーロッパ革命と日本の明治維新、『共産党宣言』と『資本論』第一巻の間)にヨーロッパシステム・ワールドから「大西洋の西」へと変貌した資本主義は、非ヨーロッパ文明だけでなくヨーロッパ文明自体も破壊し、数十年で著しい成果を達成しました。
「ダーシャの図書館」ダリア・ドゥギナ31歳の誕生日に
「ウラジーミル・ダル」出版社が始めた「ダーシャの図書館」という書籍シリーズは、ニコライ・グミレフの「英雄的抒情詩」の出版によってスタートし、その象徴的な意義を持っています。困難な闘争を経て、文明の根源とアイデンティティへと立ち返る新生ロシアの英雄、ダーリヤ・ドゥギナは、無私無欲で祖国を愛し、若くして祖国とその勝利のために命を捧げた愛国者であるばかりでなく、キリストと教会に最後まで忠実な深い信仰の正教徒であり、洗練された知識人、哲学者、文化・芸術の愛好家兼鑑定家でもあります。彼女は、ダーリヤ、マリア、スヴェトラーナ、ナタリア、ユージニア、カトリーヌ、イリーナ、アンナ、ソフィア、ワシリサ、ヴァルヴァラ、タチアナといった無数のロシアの女性たちに、外部から押し付けられた低俗で原始的な女性像とは異なる、新たな女性らしさの模範を示しています。彼女の特別な選択は、伝統とその価値観、科学、知性、意志、民族への活動的な愛、そして国と権力への献身と、始終一貫して結びついています。彼女は、自己中心的で堕落し、皮肉屋で、自分と自己のキャリアにのみ関心を持つ女性ではなく、貞操の理想を尊び、愛情深く、苦悩を抱え、思慮深く、繊細な少女です。これこそが、ロシアの「母なる娘」の真の姿です。
「メジューモニック時代のサバイバル指南書」アレクサンドル・ドゥーギンの著書『第4のロシア』について
2022年秋に出版されたアレクサンドル・ドゥーギンの『第四のロシア:反ヘゲモニー・ロシアのコンセプト』は、政治学、社会学、経済学のエッセイ集で、収録された42章は、2ページに満たないものから数十ページに及ぶものまで、量的にも時期的にも幅広い範囲に及んでいます。2008年から2009年、2018年、2019年、2021年といった複数の年にわたり執筆されたこれらの作品は、いくつかの問題がどれほど切実で緊急性を帯びていたかを今や冷静に振り返ることができるため、現在のタイミングでの出版が適切であると言えるでしょう。なぜなら、これによって私たちはロシア社会や世界全体が過去数年間でどのように変化したか、または変化していないかをより客観的に評価する機会を得るからです。